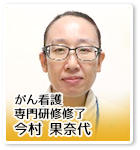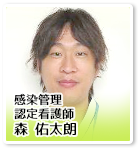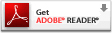スペシャリスト
診療看護師 小川 喜久恵

特定行為とは、傷の処置、ドレーン管理や抜去、輸液管理などを含み、現時点で21区分38項目の行為が定められています。
大学院卒業後、2年間各診療科をローテートし、現在は救急科に所属しています。主な業務としては、各病棟をラウンドし急変リスクの高い患者様がいないかや看護上の相談などを受けています。
また、救急外来患者様の対応、必要な医療処置の実施、カンファレンスへの参加など医師とともに患者様の診察や処置などを行いながら、学びを深めています。
看護と医学的な視点で患者様の全体像をとらえ、医師や看護師、その他のメディカルスタッフと協働し、よりよいチーム医療の提供を目指しています。
診療看護師 中山 由理奈

診療看護師の役割は、医師や他職種と連携・協働を図り、一定レベルの診療を自律的に遂行し、効果的、効率的かつタイムリーに症状マネジメントを実施することにより患者様の QOL の向上を図ることです。
看護師としてのスキルに加えて、医療の知識や技術について学んできたことを活かし、医療現場のタスクシフトに加え、医師や他職種の橋渡しなどを行なっていきたいと思います。
また、患者様やそのご家族が安心して医療を受けることができるよう、チームの一員としてコミュニケーションを図りながら活動していきたいと思います。
現在は、主に救急外来の患者様の対応などを行わせて頂き、学びを深めております。安全安心な医療提供ができるよう、精一杯努めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
がん看護専門研修修了 今村 果奈代

がんと診断された時から、患者さんやご家族は治療に悩んだり、迷ったり、様々な問題に直面します。
患者さんやご家族が抱えている問題に早く気づくために、当院では、『がんスクリーニング』を行っています。
現在は、入院患者さんを対象に行っており、身体面、精神面、社会面、スピリチュアルな面から、問題を抱えている患者さんやご家族をサポートできるように取り組んでいます。
感染管理認定看護師 森 佑太朗

認定看護師は実践・指導・相談の3つの役割があります。兼任の強みを活かし、スタッフのロールモデルとなり、スタッフへ直接的指導や教育を行うことで部署全体の感染対策の質向上を目指しています。
感染管理認定看護師として患者さんだけでなく周囲の環境にも目を向け、患者さんが安心安全に入院生活を送ることができるよう取り組んでいます。
感染対策室での活動を通して、病院全体でより良い感染対策を実践することができるようICTのメンバーの一員として貢献していきたいと思います。
がん化学療法看護認定看護師 井手 千佳子

がん化学療法を受ける患者さんが、治療を安全に受けることができ、治療による副作用症状のマネジメントを行い、患者様・ご家族様がセルフケアを実践できるよう支援することや、院内の看護師の抗がん剤治療に対する知識、技術の向上を目指し、指導や学習会を行っています。
近年様々な抗がん薬の開発が進み、従来の殺細胞性抗がん剤とは全く異なる免疫チェックポイント阻害薬などが承認適応され、治療の選択が広がってきました。

がん化学療法を安全・安楽・確実に行うため、チーム医療として医師や薬剤師などと協同し、患者さんが自分らしい生活を送りながら、治療を受けることができるよう、 個別性を活かした看護の提供を心がけていきたいと思います。
皮膚・排泄ケア認定看護師 南川 栄子

活動の内容はそれだけにはとどまらず、高齢者の脆弱な皮膚に生じる皮膚裂創(スキンテア)、酸素マスクなどで生じる医療機器関連圧迫創傷、失禁による皮膚障害などの予防とケアや、失禁などの排泄に関わる事など多岐にわたっています。皮膚の障害は痛みを伴うものがほとんどです。
ケアを行い、治癒していく経過の中で、患者様の痛みが軽減し、QOLがより良いものへと変化していくことで、患者様に喜んでもらえる、そんな笑顔がケアのやりがいに繋がっています。
褥瘡発生ゼロ、スキンテアゼロに近づくようにシリーズで勉強会を行っていき、スタッフ全員でより質の高い皮膚・排泄に関わるケアを提供できるように努めていきたいと思います。
集中ケア認定看護師 河上 ひとみ

集中ケア認定看護師の役割は、生命の危機状態にある患者に対し、病態変化を予測した重篤化の予防や二次合併症の予防および社会復帰に向けた看護実践を行うことです。
毎週月曜日に呼吸ケアサポートチーム(RST)でラウンドを行い、患者の呼吸状態の安定化を図るために活動を行っております。また、院内心肺停止症例の削減を目標にRRSという院内救急対応システムの活動にも力を入れています。
今後も患者の重症化を回避できるような取り組みを充実させていきたいと思っています。
緩和ケア認定看護師 小森 康代
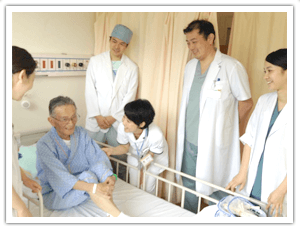
今の日本は、2人に1人はがんと診断される時代になっています。さまざまな治療を受けながら、年々「がんと共に人生を歩む人」は増加しています。「緩和ケア」は、そのような人が、がんと診断されてからも自分らしく豊かに暮らすことができるようサポートをしていくケアです。
具体的に内容のお話しをしましょう。緩和ケアは、患者さんの痛みや悩みなど「身体や心のつらさの緩和」を行います。がんの治療を受けながら、がんそのものの痛みや治療のつらさに、さまざまな専門職がチーム(緩和ケアチーム)を組んで対処します。また、心理的な不安や生活面での悩み家族の悩みも含めてサポートしていきます。 患者さんと家族が、がんと向き合い、「自分の人生を自分らしく生きる」ことを支えるケアの提供を目指し、日々活動しています。
緩和ケア認定看護師 山本 愛

緩和ケア=終末期というイメージが強いかもしれませんが、緩和ケアは、がんが進行してから受けるものではありません。がん患者さんは、がん診断初期から様々な『いたみ』を感じているといわれています。
私は、患者さん・ご家族との関わりを大切にし、少しでも『いたみ』が緩和されるように看護を提供していきたいです。
緩和ケア認定看護師の役割が果たせるように頑張ります。よろしくお願いいたします。
緩和ケア認定看護師 近松 あや

緩和ケア認定看護師の役割は、患者さんやご家族の体や心のつらさを和らげ、できる限り普段通りの生活を送ることができるようサポートを行っていくことです。
私は患者さんが病を抱えながらも、1 日 1 日をその人らしく生きることができるよう支えていく看護を心がけています。また、患者さんやご家族が大切にしていることや価値観を尊重できるように、常に医療チームのみんなで考えながらケアを実践していきたいと思っています。
現在、看護師長として病棟で勤務をしていますので、患者さんの苦痛緩和を図り、穏やかな日々が過ごせるようケアの方法を病棟看護師と共に考え、実践していきたいと思います。
認知症看護認定看護師 池田 貴子
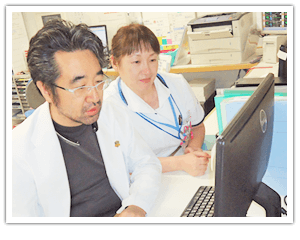
急性期病院では、認知症者の意思や尊厳が守られることよりも高度専門治療や術後の管理が優先され生命の維持や安全を保障することに重きをおくため、やむを得ず抑制されている現状にあります。私自身、手術や治療を安全に進めるために抑制することにジレンマを感じ、他に方法はないか、この現状を何とかしたいと思い認定看護師の資格を取得しました。
DST活動では病棟での対応困難な事例について依頼を受け、病棟スタッフと一緒に検討しています。患者さんが穏やかに過ごすために、患者さんが今置かれている状況を一つ一つ紐解きながら考えています。、家族や本人の思いを聞くことを大切にして関わりMSWや臨床心理士と一緒に入院前の生活状況の確認や退院後の生活を見据えた支援の方法を検討しています。
私は、認知症看護を実践するには日常のケアを一つ一つ丁寧に行うことが大切だと感じています。認知症患者さんとゆっくり時間をかけて関わることは難しい環境かもしれません。しかし、関わり方や声のかけ方、環境調整など、できることはあると思います。私たち看護師が笑顔で明るく楽しんで看護をすることが認知症患者さんの安心につながります。みなさんと一緒に笑顔のみえる認知症看護を実践していきたいと思います。
クリティカルケア認定看護師(救急看護) 中島 舞

突然の病気や事故により苦痛や不安を抱えている患者さんだけでなく、ご家族の擁護者としても苦痛や不安が少しでも軽減できるよう、全人的なケアを実践したいと思い、2021年に救急看護認定看護師の資格を取得し、同年度に特定行為研修を修了し、2022年4月より活動をしています。
救急看護では、患者さんの身体的側面だけでなく、患者さんやご家族の心理的側面も学ぶことができました。現象だけでなくあらゆる背景にも目をむけて、看護師としてどういう介入が必要なのかを他のスタッフとともに考えることを日々心掛けています。

また、当院は災害拠点病院であり、災害時に備えて災害派遣医療チーム(DMAT)の隊員として院内での災害訓練に取り組み、院外の訓練にも参加をしています。